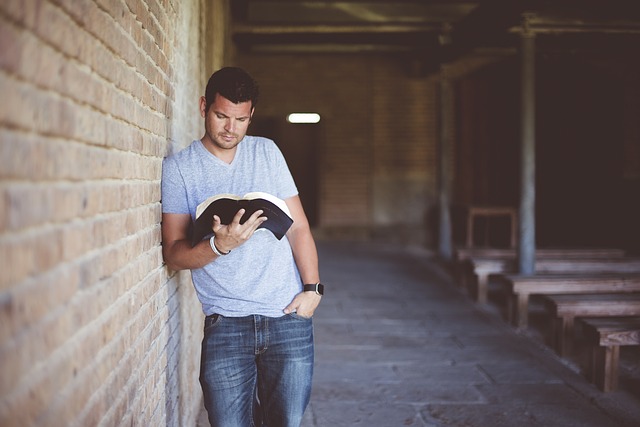
みなさま、こんにちは。先日、岡田斗司夫さんの著書『いいひと戦略 超情報化社会におけるサバイバル術』を読みました。中田敦彦さんのYouTube大学でも紹介され、読者レビューも高評価だったので、以前から気になっていた一冊です。読了後の感想は、「これは面白い!」。本書は、現代社会を生き抜くための生存戦略として、「いいひと戦略」を提唱しています。
【目次】
- 「いいひと」戦略とは?
- 「嫌な人」の特徴
- 「いい人」になるためのステップ
- なぜ「いい人」が評価されるのか?
- 「いい人」を演じるということ
- 情報化社会における「いい人」の重要性
- まとめ:「いい人」戦略で人生を切り開く
「いいひと」戦略とは?
この本では、現代社会を生き抜くための生存戦略として、「いいひと戦略」が提案されています。「いいひと」は、人としての評価がいずれ仕事を生んでくれる。この考え方は、必ずしもすべてに当てはまるわけではありませんが、知っておいて損はないと思いました。
「嫌な人」の特徴
「いい人」になるためには、まず「嫌な人」にならないことが大切です。本書では、「嫌な人」の特徴として、以下のようなものが挙げられています。
- 欠点を探す
- 改善点を見つけて提案する
- 陰で言う
- 悪口で盛り上がる
- 悲観的・否定的になる
- 特定のグループで固まる
ドキッとしました。いくつか当てはまっているかも…。知らず知らずのうちに「嫌な人」になっている可能性もあるので、気をつけたいと思います。
「いい人」になるためのステップ
では、具体的に「いい人」になるにはどうすればいいのでしょうか?本書では、以下のステップが紹介されています。
- 助走:フォローする
- 離陸:共感する
- 上昇:褒める
- 巡航:手伝う、助ける、応援する
- 再加速:教える
- 軌道到達:マネー経済から抜け出す
意識すればできそうですが、それなりの努力は必要ですね。「褒めない」「一人が好き」「人に興味がない」「自己中心的である」。そんな人にとって「いい人戦略」は苦痛かもしれません。
なぜ「いい人」が評価されるのか?
会社にいると、一緒に仕事をしていて不快になる人もいれば、居心地の良い人もいます。その違いは?理由はたくさんあると思いますが、一言で表現すれば「いい人」と言えるのではないでしょうか。私の会社にも、根っからいい人がいます。明るく、世話好きで、他人の悪口なんて言いません。批判的なことは一切言わず、とにかく褒める。損得勘定なんてこれっぽっちもないような人です。
「いい人」は他人に対して親切で配慮があり、信頼と尊敬を集めやすくなります。これが仕事の場面でも個人の生活でも、大いに役立つのです。また、社会全体が協力と調和を重視するため、「いい人」は周囲の人々から高く評価されがちです。人間関係において他者を尊重し、協力する姿勢を持つことは、集団の中での成功や幸福に繋がります。
「いい人」を演じるということ
実は、ここで言う「いい人」とは、必ずしも本当にいい人である必要はありません。むしろ、いい人を「演じる」ことによって、自分の評価を上げていくことが重要です。もちろん、実力が伴っていることが前提です。「いい人」というイメージを持ってもらい、評価を上げることが大切ですが、実力がなければ評価を下げることにもつながります。

情報化社会における「いい人」の重要性
情報化社会となった今、情報はSNS等で簡単に広がるようになりました。例えば、食べログやFacebook、YouTubeなどにより、あっという間に情報が共有されます。私もよくネットショッピングをしますが、商品レビューなどを参考に購入しています。評価が良ければ購入しますが、悪ければ買いません。また、フォロワーが多ければ多いほど、影響力があるとも言えます。「いい人」というイメージを持ってもらい、評価を上げることが大事です!
まとめ:「いい人」戦略で人生を切り開く
この記事では、「いい人」戦略の重要性について解説しました。「いい人」戦略は、現代社会を生き抜くための有効な手段の一つです。「いい人」になることで、人間関係が円滑になり、仕事も成功しやすくなります。もちろん、実力を磨くことも大切です。「いい人」戦略と実力を兼ね備えることで、より豊かな人生を送ることができるでしょう。ぜひ、「いい人」戦略を実践して、より良い人生を歩んでください。最後までお読みいただき、ありがとうございました。